【1978年】~都ぞ弥生 ~おごそかに北極星を仰ぐ哉~
北海道大学はコスモポリス
●札幌南高校を卒業して北海道大学に合格した私は、北海道大学の学生の多様性に驚かされた。当時、北海道大学は道内と道外の学生が半々であった。関西方面から来た学生は関西弁を直そうともせず、堂々と話していた。九州から来た学生はどことなく控えめな態度で好感が持てたためか、九州出身の人とはウマがあった。教養時代一緒に過ごした仲間に、長崎県島原出身の木村君と大分県四日市出身の古野君という2人の友人がいた。
北海道大学教養学部では、ドイツ語の岡崎先生が担任であった。第2外国語はドイツ語を選んだのだが、教養のクラスは外国語選択で分けられていた。ドイツ語選択のクラスは女子がとても少なく後悔した。女性はやはりドイツ語よりフランス語だったのだ。
教養時代の最大のイベントは学園祭の模擬店であろうか。クラスでおでん屋をやることになり責任者となってしまった。だが、私は高校時代、生徒会活動ばかりやっていて模擬店の経験がなく、女学生からリーダーシップがないと直接非難され非常に落ち込んだことを覚えている。
授業そしてアイドルと映画三昧の日々

テレビドラマでは、大学生といえば、「暇」というイメージであったが、必修単位も多く、取らねばならない単位数もかなりあった。かつ、成績順で希望する学部を選択できるシステムだったため、授業をサボることもあまり出来ず、かなりまじめな学生生活を送っていた。
それでも授業が終わると、狸小路のビリヤード屋に行ったり、初めてパチンコにも打ち興じたり、深夜まで飲んで友人の家に泊めてもらったり。それなりに青春を謳歌していた。いつも遊んでいたメンバーは上野君、坂東君、寺田君、野村君、小山君、古野君、木村君の7名。
中でも小山君は熱烈的なキャンディーズファンで、彼に感化されて私もいつしかキャンディーズファン(特に蘭ちゃん)になっていた。蘭ちゃんのブロマイドを財布に入れていたのもこの頃だ。その後、薬師丸ひろ子が好きになって、ついにはコンサートまで行った。
また、寺田君、野村君とは汽車通仲間でもあったので、札幌駅の地下にあった映画館で二番煎じで回ってくる映画を見ていた。確か学生300円くらいだったと思う。
映画館は決して綺麗とは言えないが、いつも満員だった。ここで、薬師丸ひろ子や原田知世主演の、当時人気絶頂だった角川映画など、さまざまな邦画を観ていたが、でも一番感動したのは、「砂の器」だった。満員御礼の劇場で、立ち見で最後まで感動して見入っていた。あの時の人混み、観客の雰囲気が忘れられない。今でも映画館へ足を運ぶのはこの体験によるものかもしれない。映画は自宅で観るよりも、多くの人と一緒に観た方が絶対に感動するものと肌で感じたものである。
長崎の鐘
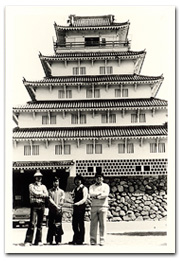

入学後2年生3年生との対面式があったが、野次と怒号の中、いきなり先輩の一部から1年生に生卵が投げつけられるという洗礼を受けた。
今でもなぜ野次と怒号が生じ、生卵だったのかわからない。
全校集会も常識を超えていた。まずクラス毎の整列というものがない。生徒は、三々五々体育館に集合して、無秩序にたたずんで、校長先生の話を聞くのである。
そして法学部へ
教養学部も2年の後半には、各学部への移行期を迎えた。私は、一生懸命「優」を集め、問題なく法学部に進学した。そして、司法試験を目指す先輩が多くいる歴史ある北大法律相談室に入室したのである。
【1980年代】給湯族 ~北大にはかつて「給湯族」と呼ばれた若者たちがいた~
司法試験合格をめざして、ひたすら勉強をした日々

私が北海道大学法学部で司法試験の勉強をしていた1980年代。同学部には「給湯族」と呼ばれる人々がいた。「給湯族」とは、朝9暗から夜10時まで自習室でひたすら勉強をし、昼休みやタご飯時期に給湯室でコーヒーを飲みながら、法律問題について議論するのを日課とする学生たちであった。現役学年は少なく、ほとんどが卒業生で、他大学の卒業生も含まれていた。
当時の北海道大学の司法試験合格者は、毎年3名から6名程度だったが、そのほとんどが「給湯族」出身者だった。「給湯族」は仲間から合格者が出ると、ゼミをしてもらったり、仲間同士でゼミを組んだりして受験のノウハウを受け継いでいった。
北海道大学の懐の深い大学だった
「給湯族」に特に人気のあった大学の先生は、民事訴訟法の小山昇先生である。小山昇先年は民訴法の大家でありながら、現役生、卒業生の分けへだてなく答案を添削してくださった。また、憲法の中村陸男先生(現北海道大学学長)や大塚龍児先生など、本当に親身になって受験生の面倒をみてくださった先生も人気があった。北海道大学法学部は、学年の身分を持たない「給湯族」も受け人れる懐の深さがあり、そのことが北海道大学の良さだと思っていた。「給湯族」はみな感謝して勉強し、合格したら、後輩を一生懸命指導して恩返しをしていった。
「給湯族」と「給湯室」の消滅
ところが、私が合格した後、「給湯族」は消滅した。現役の学年らから、何の資格もない「給温族」が自習室や給湯室にたむろしているのは目障りであるという訴えがあったのだ。正諭を言われたら「給湯族」は弱い。給湯室は演習室とされ、「給湯室」という場所もなくなった。「給湯族」消滅後、北大の合格者が激減したのは当然の結果であった。氷河期の到来である。北大の司法試験受験生は、受験予備校に通い始めるようになった。
「給湯族」の心は生きている
司法試験受験生の合格者の累計が1,000名になり、法科大学院(ロースクール)の設立が決まってから、北海道大学の合格者は20名を超えるようになった。
これは北海道大学の先生方が司法試験受験生を応援し始めたからである。そしてその中心になってくださっているのは、大学院生だった当時、給湯室にちょくちょく顔を出してくれていた先生たちだそうである。
今、弁護士になって役立っているのは、司法試験予備校のテキストで習ったことではない。「給湯室」で、お互いに興味に任せて法律論を戦わせていた時の思考方法であり、議論方法である。一見、無駄な議論のようだが、今になって振り返ると本当に役立っている。どんな問題にも解決策はあるし、どんな不利な状況でも理屈を考えることができると信じているのは、その時の経験からである。また、「給湯族」の間で培われた人間関係は一生ものであり、生涯の私の財産でもある。
【1980年代】私の司法試験奮戦記
法学部の自習室で学び司法試験という壁に挑む

北海道大学法学部を同期と一緒に卒業せず、司法試験にチャレンジする道を選んだ私は自宅では勉強をせず、毎日法学部の自習室に通った。自習室には、私のように司法試験をチャレンジする先輩が多数いて、緊張感を持って勉強できるからだ。また、休み時間になれば、給湯室と呼ばれる学生の休憩室でお茶を飲みながら、さまざまな法律論を戦わせることができた。
当時、司法試験は約2万人が択一式試験を受験し、約5,000人が合格して、論文試験を受け、500名に絞られる。さらに口述試験で50名程度がふるいにかけられて落とされ、残りの450名となり、ようやく最終合格する。合格率2%前後、合格者の平均年齢29才という日本で一 番難しい試験であった(ちなみに現在の全体の合格は2,000名程度、北海道大学ロースクールの合格率は30%程度)。
択一式試験は、マークシート形式の90問だったが、受験経験を重ねるうちに、75問、60問と減っていき、その分問題も長文化し、難しくなっていった。合格率25%だが、ボーダーラインには大人数の受験生がひしめき、最大難関の論文試験に力を入れすぎて、取りこぼしてしまうことがよくある試験だった。
布団にくるまって択一・論文試験に泣いた歳月

5月の第2日曜日の母の日に行われるこの試験で落ちると、来年まで一年間待たねばならず、この上なく辛い。一番辛かったのは合格前年に択一試験で落ちた時だ。この時は、論文に相当自信があっただけに本当に辛かった。布団にくるまって何週間も過ごして現実逃避した。立ち直るのに何週間もかかった。
論文試験は、憲法・民法・刑法・商法・訴訟法(民事ないし刑事)・法律選択科目(私は国際私法)・教養科目(私は政治学)の7科目を4日間かけて各2時間ずつ解いていくという過酷な試験だ。私はここで何度も足踏みを食わされた。
当時、成績通知制度が始まって、自分が受験した司法試験の各科目の成績を知ることができた。私は受験して数回目で総合A評価を得ることができた。A評価とは、論文受験生のうち合格者を含めてトップ1,000番にいるということだ。以下、500人刻みにB・C…Gとなる。私は、このA評価を3年連続とるという自慢できない名誉を得た。つまり、毎回チケットを購入するために列に並ぶが、直前の人で売り切れとなってしまったということを繰り返していたのだ。
論文の合格発表は合同庁舎の掲示板に紙が貼られる。合格する前々年のことだが、結構自信があったので、発表時間に遅れて悠々と掲示板を見に行ったのだが、すれ違った受験仲間が憐れむような目線を私に投げかけていったことを今でも鮮明に覚えている。結果は不合格。もちろん、この時も布団の中で数週間過ごした。
涙が頬を伝う喜びも束の間、プレッシャーが押し寄せる数カ月
3年連続Aに留まっていた私は、合格した先輩に相談したところ、複数の科目で大きく点数を稼ぐようアドバイスを受けた。その年、私は憲法と刑法に絞ってゼミを組み、過去問を中心に徹底的に論点を掘り下げ、理想的な論文答案を作成することに没頭した。
論文対策に力を注いだため、択一試験は薄氷を踏む思いであったが、その分論文では実力を発揮できた。その年の論文の合格発表の時は時間前に陣取り、掲示板が張り出される瞬間を目撃した。巻紙の一番上を画鋲で留めて、クルクルと解きながら掲示していくのだが、その途中に自分の名前を発見したときは、うれしくて飛び上がりたい気持ちと安堵感が一気に広がり、涙が頬を伝わった。
合格の喜びに浸って、家に戻ったが、その夜当たりから今度は一気に口述試験に対する不安感で押しつぶされそうになった。落とされるのは1割程度。その1割に自分が入らないとも限らない。論文試験は6月、合格発表は秋。その間、口述対策ゼミを組み、準備は万端だったのだが、ここまで来て絶対落ちたくないという気持ちが非常に強くなり、それがプレッシャーとなった。
口述試験は東京の最高裁研修所で行われた。一週間一日1科目から2科目の口述試験だった。試験官の前に座らされ、さまざまな法律問題を受け、その質問に臨機応変に答える。目の前には六法一冊。長丁場であったが、実際に受験してみると、給湯室の議論で鍛えられていたので、むしろ楽しく受験することができた。そして、無事合格を果たす。
懐かしく幸せな歳月だったモラトリアム時代

合格したのは、昭和天皇が崩御される前年の昭和63年(1988)のことだった。受験開始が法学部移行期の昭和52年(1977)だから、チャレンジすること11回でようやく論文に合格したことになる。長い受験生活だった。しかし金も地位もなかったが、野心に近い希望や時間はふんだんにあった。あれほど自由に時間を使えた時期はない。親の脛をかじりながら過ごしたモラトリアム時代だったが、受験の苦しみの思い出よりも、今は楽しい思い出しか残っていない。ある意味幸せな時期だったような気もする。
【1989年】私の司法修習生時代〈その1〉前期司法研修所生活
晴れて合格率2%の難関を突破して司法研修所へ

平成元年、晴れて司法試験に合格した私は、初めて親元を離れ、東京へ向かった。千葉県松戸市の近くの馬橋にある司法研修所の寮に住みながら、東京台東区の湯島にある司法研修所に通うという前期研修所生活を始めた。
当時は、合格者は500名足らずで、10組に分かれて研鑽を積んだ。研修所は旧(三菱)岩崎邸内にあり、環境も良かった。当時の合格者は今の4分の1程度。かつ修習期間も倍の2年間だったから、時間も予算も余裕があった。カリキュラムも緩やかで、教養を高めるための観劇などもあり、生まれて初めて歌舞伎や人形浄瑠璃なども見ることができた。
当時はロースクールも受験回数制限も無かったから、30歳だったとはいえクラスでは平均年齢付近だった。現役合格者から苦学して何年もかかって合格した人までいた。また、今のように地域毎のクラス分けはなく、全国各地から修習生が集まり、まさに多士済々であった。
授業は民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の6科目。主なカリキュラムは講義と起案。講義の後、白表紙と言われる資料を渡され、裁判科目なら判決文、検察科目なら最終弁論や起訴状、民事弁護なら訴状や最終準備書面、刑事弁護なら最終弁論を作成する。起案には研修所内で朝から夕方までまる一日使って作る即日起案と、自宅に持ち帰って翌日までに作ってくる自宅起案の2種類があった。
楽しくも厳しくもあった寮生活
寮はJR常磐線の馬橋駅から歩いて10分程度のところにあった。そのまま千代田線に入る乗り換えなしの便利な場所だった。しかし、北海道で育った私 には、満員電車が苦痛だった。身動きが取れない。そんな電車通勤を平気でこなしている東京の皆さんが本当に立派に見えたものだ。
寮には大浴場があり、朝晩のご飯も用意されていたので人気があり、定員オーバーだった。このため本来は1部屋なのに、間を板で仕切り、荷物棚を作り、無理矢理2部屋にしていた。隣人の息づかいまで聞こえてくるという住環境だった。寮は便利で本当に居心地良かったが、この部屋の造りには本当に泣かされた。
隣人の修習生が無類の酒好きだった。福岡出身の彼の元には、地元出身の友人やクラスの酒好きがたむろして夜中遅くまで酒を酌み交わしていた。酔っているから、こちらが寝ようと思っても配慮など一切なし。自衛策として耳栓をして寝ていたが寝付けない日々が続いた。
研修所教官は皆、素晴らしい現役の法曹

各科目の教官は皆現役ばりばりの法曹であり、個性的な方々が多かった。民事裁判は遠藤裁判官、刑事裁判官は安井裁判官、刑事弁護は石井弁護士、民事弁護は北村弁護士・清水弁護士(後期)、検察は吉村検事である。
当時は、どの教官もお宅訪問を受け入れてくれていた。私は法曹の私生活を知りたくて全教官の自宅訪問に応募し、実際に全教官のお宅へお邪魔することができた。毎回かなりのごちそうを準備してくれて、教官の奥様は大変だったと思う。どの教官もご自宅でリラックスした普段着の姿を見せてくださった。自分の将来の生活状況や、合格後の進路について具体的なイメージを持つことができたという意味では非常に貴重な機会であった。
青春の再来
最初は東京の水に慣れず、おなかを壊し続け、免疫がなかったのか蚊に刺され大きく腫れていたものだが、徐々に体調も良くなり、隣人の音もさほど気にならない程、図太くなっていった。飲み会で遅くなってから大浴場に行くと、既にぬるま湯状態だったが、構わず浴びて寝たこともある。土日は休みだったので、友人の修習生と鎌倉の江ノ電に乗ったり、葛飾柴又の帝釈天に行ったり、コンサートに出かけたりと楽しく過ごしていた。まさに、青春の再来だった。
そして、梅雨が明ける頃には研修所での修習を終え、実務修習に向かうことになった。実務修習地は地元の札幌。札幌の修習生は当時14名。最初は検察、その後は刑事弁護、民事弁護、そして弁護修習と続くが、それぞれの修習期間は約3カ月程度で、約1年間に渡り、じっくりと実務を学ぶことができた。
皆で歌ったパラダイス湯島

思えば、前期研修所生活では、法曹の基礎をみっちりたたき込まれた。法曹とふれあったのは、研修所の教官たちとの出会いが最初だが、どの教官も法曹としての自覚と自信に満ちていて、魅力的な方々ばかりであった。研修所の教室で勉強していると大学ではなく、タイムマシンに乗って、10年以上前の高校生時代に戻ったような気持ちになった。
当時、修習生歓迎会なる企画があり、ほぼ全員の修習生が参加したように思う。その時、歌詞カードが配られて替え歌を歌わされたのを鮮明に記憶している。それは、♪ようこそここへ…で始まる、光GENJIの「パラダイス銀河」の替え歌だった。今でも懐かしのヒット歌謡番組でこの曲を聴くと、研修所の生活が鮮明によみがえってくる。
【1989年~1990年】私の司法修習生時代〈その2〉中期司法研修所生活
検察修習で学んだのは被疑者の信頼を勝ち得る取り調べ

当時の修習制度では、夏までみっちり訴状作成や弁論要旨作成などの基礎訓練を受けた後、実務修習地で民事裁判、刑事裁判、検察、弁護の各科目について裁判所や検察庁、そして法律事務所で実地訓練を行う仕組みになっていた。私が配属されたのは地元札幌地方裁判所であった。
最初の修習は検察である。検察修習では実際に被疑者を取り調べて調書を作成したり、公判に立ち会うなどする。その中でも最も貴重な体験となったのは取り調べ修習である。当時は札幌に配属される修習生はわずか14名(今は100名弱)であったので、修習生二人で組になって取り調べを担当するが、被疑者の数も10名近くとなり、非常に忙しかった。覚醒剤や強姦、強制わいせつ、窃盗などの被疑事件を担当したが、一番記憶に残っているのは当初否認していた窃盗事件であった。いろいろと調べを進めていくうちに、自白をしてもらえることができたのである。
取り調べは、被疑者からいかに信頼を勝ち得るかの勝負であると確信した。被疑者のことを考えた上での取り調べこそ被疑者の心に響くものであり、上から目線ではなかなか良い取り調べはできないことを悟った。検察修習は、活気のあるもので当時修習担当だった新庄検察官の明るい人柄も手伝って、検察官という仕事には大いに魅力を感じたものである。
尋問に対する裁判官の評価を学んだ裁判修習
約4カ月の検察修習を終えると、次は刑事裁判修習である。被疑者を糾弾する側から裁く側に回るわけである。私の修習は刑事一部で、龍岡裁判長、若原右陪席裁判官、伊澤左陪席裁判官で構成されていた。龍岡裁判長は修習生を自宅に招いてくれて、裁判官の日常生活を見せてくださった。また、合議事件などでは刑事裁判官の悩みを垣間見ることが本当に勉強になった。
さらに、数カ月後には民事五部に配属となった。若山裁判長、山下右陪席裁判官等の下で判決起案などをさせていただいたが、一番勉強になったのは証人尋問後の裁判官の尋問に対する評価である。弁護士になってみると、自分が行った尋問を裁判官がどのように評価しているのか関心がある。しかし、それを裁判官に尋ねる訳にもいかない。修習生のときは裁判官から目の前で実施された尋問の評価をすぐに聞けるわけだから勉強にならない訳がない。
どんなことがあっても休んではならない
さて、検察修習では目が回るような忙しい修習だったのが、裁判修習ではじっくりとした修習となり、時間がゆったりと流れていった。しかし、いよいよ弁護修習が始まると、その時間の流れは想像以上に激しく厳しいものに変わった。
当時修習を担当してくださる修習担当の弁護士は担当弁護士が引くくじで決まるのが習わしで、私は磯部憲次先生のところで修習することに決まった。
磯部憲次先生の指導は極めて厳しいものであった。磯部先生からまず言われたのは「弁護士は健康こそ最も大事で、どんなことがあっても風邪であっても交通事故にあっても這ってでも仕事に出なければならない」ということだった。
ところが、間が悪いことに言われてすぐに風邪を引いて休む羽目になった。風邪で寝込んでいたら、磯部先生から電話が来て、やりかけの起案を完成させないまま事務所を休んでしまったことについて注意を受けたのである。
また、磯部先生が事情を聴取しているときに私が介入し、他愛もない話題を顧客に話しかけ場を和ませることがあったが、顧客が帰ってから、途中で話の腰を折るような言動を慎むよう諭された。このエピソードは修習から20年以上経ても記憶に残っているのだから、よほど当時の自分には堪えたのであろう。
足を休めないで歩くそれが弁護士

考えてみれば、検察修習、裁判修習と大過なく過ごし、中だるみしていた時期だったのかもしれない。 他の事務所に当たった修習生は、ほとんど事件が無く、ゆっくり過ごしているという。話を聞く度に羨ましいと思ったものだ。
ところが、今思えば磯部事務所で厳しく指導されたことが弁護士になって本当に貴重な経験だったと思える。磯部先生には、弁護士の基本姿勢を教わった気がする。
磯部先生は開業以来一日も健康上の理由で仕事を休んだことは無い。そのことを自慢されていたが、私も現在までノロウィルスに罹患したときに休んだ一日を除いて、一度も風邪で仕事を休んだことがないのが自慢の一つだ。
磯部先生は厳しいだけでなく、よくすすきので、おいしい食事をご馳走してくださった。事務所旅行では返還前の香港マカオにも連れて行ってくださった。生まれて初めての海外旅行だった。
また、「北海道を歩こう」大会には歴代の修習生が参加しているということで、真駒内から支笏湖までの36kmを、恵庭峠を越えて歩く大会にも参加した。こんなに長い距離を歩くのは初めてだった。それでも一歩ずつ一歩ずつ「とにかく足を休めないで歩く、それが弁護士」という思いをかみしめながら完歩したのを覚えている。
【1990年】私の司法修習生時代〈完結編〉後期司法研修所生活
ピリピリも無理がない?噂の「最終試験」

私の修習生の頃は、修習期間は2年間という長丁場だった。研修所の前期修習で実務家としての基礎を習い、実務修習で習得し、また研修所に戻って後期の4カ月で、それを再度まとめ上げるという形だ。そして、最後に待ち受けているのが、2回試験という「最終試験」である。最近はこの試験でかなりの人数が落ちるが、当時は1名か2名程度であった。しかし、自分がその1名か2名に入らないという保証は何一つ無い。
当時、裁判官や検察官志望者はこの時の試験成績がその後の出世に関係があるという、まことしやかな話が出回っていたので(それは実は本当らしい!)、任官志望の修習生は、どうしてもピリピリとした雰囲気となる。一方、弁護士志望の修習生は気楽だが、クラス全体の雰囲気はどうしても張り詰めたようになり、明るく楽しい前期修習とは雲泥の差であった。
無味乾燥の後期修習唯一の楽しみは……
後期修習時代は、連日起案起案の連続で、殺伐としたかなり無味乾燥な時期だった。そんな心を癒やしてくれたのはクラシック音楽だった。休みのたびに秋葉原まで出かけて『レコード芸術』で年間ベストテンに入ったCDを購入して、ディスクマンを利用して寮で聴いていた。聴いていたのは、モーツァルトの宗教音楽とピアノソナタ、バイオリン協奏曲が中心だった。これらの曲を聴くと修習生の頃をよく思い出す。
そういえば、中野サンプラザまで一人で出かけてバレエを観に行ったこともある。最もクラシック音楽に近づいたのは後期修習の頃だったように思う。海外でオペラを見るようになったのも、この時期の影響があるのかもしれない。
後期修習は、目の前にある2回試験対策も大事なのだが、就職後のことも気になって、なんだか落ち着かない。このような時期だからこそ、クラシック音楽が聴きたくなったのだろう。
余談だが、修習時代はモーツァルトをよく聴いていたのだが、徐々にバッハへと趣向が変わった。仕事中にクラシック音楽を聴くことが多いのだが、バッハだと仕事が大いに捗るからだ。
合格者の多くは実務修習中に挙式する

司法試験受験合格者の平均年齢は、およそ30歳前後で、男性が圧倒的に多数を占めていた。このため合格を機に、かねてから交際していた女性と、あるいは新たな出会いで結婚する修習生が多かった。私も、実務修習中に結婚式を挙げた。
私たちは、北11条教会で挙式し、そのホールで茶話会として披露宴を行った。アルコールはなかったがオードブルとお菓子、コーヒーで会費3000円。多くの方に気軽に参加していただけ好評だった。修習生仲間の演奏会や家内の職場仲間のコーラスなど、本当にささやかだったけれど、温かい披露宴だった。
当時、千葉の松戸にあった研修所の寮には、受信専用の電話回線が数本あった。この電話は各階の廊下に置いてあり、時に寮全体に響き渡る寮長の声で電話コールがあった。しかし、100名もの寮生がいるのだから、当然回線は足りない。多くの修習生が玄関に設置されている5台程度の公衆電話で、遠距離にいる恋人や新妻と話し込む。午後8時を過ぎると、寮生たちが電話の前でちゃんちゃんこを着てしゃがみ込んで、笑顔でひそひそと話し込んでいる姿が頻繁に見られた。
ちなみに、当時は携帯電話など無く、研修所の売店にあるテレフォンカードで電話をかけるしかない。この売店のテレフォンカードの売り上げは、なんと千葉県でトップだったそうな。
試験に落ちないコツ
年が明けると、いよいよ2回試験の本番である。当時は、民事系、刑事系の2本立ての筆記試験と口述試験まであった。まさに、最後の難関である。
この試験、絶対に落ちないコツがある。それは、落ちるのはごくごく少数なのだから、おおよその修習生が考えそうなことを答えれば良い。奇をてらって少数説を採る必要は無い。そう考えれば気は楽である。しかも、弁護士になるのに研修所の成績順位は無用。
というわけで、2回試験は無事通過。結局、不合格となったのは当日風邪で試験を受けられなかった1名だけであった。
弁護士のスタートはまさに修行のはじまり
2回試験の発表があり、卒業式を終えると、いよいよ弁護士のスタートである。札幌弁護士会に登録した弁護士は全部で7名だった。私の勤務先は、実務修習中に法律相談室の先輩弁護士に紹介をいただいた中山博之法律事務所。
中山博之先生は、当時札幌弁護士会の副会長で弁護士活動に熱心な人物で、刑事弁護では全国的に知られた売り出し中の弁護士。本当の修行はここから始まった。
数々の思い出深い事件に巡り会い、本当に修羅場修羅場の連続で、今の自分の基礎が作られたイソ弁時代の5年間だったと思う。どこの事務所に進むのかではなく、いかに意味のあるイソ弁時代を過ごすかが、大切だということが後になって分かるのである。
【1991年】弁護士駆け出し時代〈 I 〉
牧歌的な札幌弁護士会の良き時代

私が中山博之法律事務所に入職した当時、札幌弁護士会は200名前後の牧歌的な団体だった。それだけに、ほぼ全員の弁護士の名前と顔が一致していた。
裁判があると大抵の弁護士は裁判所の2Fにあった弁護士控え室に立ち寄り談笑をしていた。あるいは将棋や囲碁に熱中している先輩弁護士、岡目八目で見守る弁護士もいた。
また、弁護士会では、各種委員会の後は必ずといっていいほど飲み会があり、先輩弁護士からご馳走になったものであるが、そこで話題になるのは決まって裁判官や検察官のことだった。そして最後に弁護士自身の話題だ。「目指すべき」弁護士や「なってはいけない」弁護士像が新人弁護士に刷り込まれていく。今思えばとても重要なことだったように思う。新人弁護士を大切に育てるという意識や気風が当時の札幌弁護士会にはあったのだ。
新人弁護士の歓迎会は、多くの弁護士の家族や職員が集まってアサヒビール園で行われた。新人弁護士はカラオケで歌を披露して、名前を覚えてもらうのである。私が歌ったのは郷ひろみの「よろしく哀愁」だった。当時、かなり郷ひろみに似せて歌うことができたので、結構ウケたことを覚えている。
弁護士やその家族・職員が一堂に会して大運動会も行われた。当時の大通小学校のグランドを借りて綱引きや徒競走に興じたが、これも弁護士やその家族の顔を互いに見知っているから楽しかったのだろう。
大運動会のようなアットホームな企画は後にも先にもない。札幌弁護士会の牧歌的な時代のピークだったように思う。
当時の新人弁護士は毎年10名以下、今は弁護士大量増員時代を迎え50名以上。正直、名前も覚えきれない。裁判所の弁護士控え室には今も古い囲碁台が一つポツンと置かれているが、囲碁をする弁護士は誰もいない。
厳しい遠方出張が続くイソ弁の日々
遠方の出張はたいてい「イソ弁」の役割である。稚内、紋別、静内、函館など、とにかく遠くの出張が多かった。また、単に地方の裁判所の法廷に出かけて裁判というものではなく、稚内の幌延地区まで干草を圧縮する機械を受け取りに行ったり、浦河地区まで当事者と話し合いに行ったり、函館まで朝駆けで自宅に戻った債務者の自動車を差し押さえに出かけたりと、現地での交渉や駆け引きなどを要求される場面が多かった。
ある時、稚内へは飛行機で出張したが、帰りの飛行機が丘珠から来ないことがあり、稚内からスーパー宗谷で戻ることになった。だが、当時の列車は喫煙自由の時代。数時間もの間、タバコの煙に囲まれて過ごさざるを得なかった。タバコが大の苦手の私にとって、これはもう地獄としか言い様がなかった。今も、列車に乗ると、この時のことが悪夢のようによみがえる。
先輩弁護士でも遠慮なし逆に戦闘態勢が先輩への敬意
事務所のボスである中山博之先生は、ハードワーカーで知られていた。事件の数も非常に多く、それ故、例え新人であっても甘えは許されない。最初から厳しい環境に飛び込まざるを得なかった。
そもそも法廷の当事者席に座った瞬間に、相手が先輩であろうと、法の前では対等であり、気を抜いた悪手は的確に咎められる。駆け出しの私は、相手方となった先輩弁護士が提出した書面を超えるような書面や主張をしなければという気持ちが強かった。たぶん、先輩の中には、私のことは、駆け出しのくせに態度がでかい弁護士に映っていたのではないかと思う。
私が修習した先の磯部憲次先生が、元ボスの先生と裁判で相まみえた時、相手方以上の仕事をしないと駄目だ、それが弁護士流の「恩返し」でもあると話していたことがある。
法廷で、裁判官が熱意を持って訴訟指揮をして、両弁護士が全力を尽くして戦う時、そこにはスポーツの試合にも似たすがすがしい空気が生まれる。私が法廷を仕事場の中心に添える「法廷弁護士」と呼ばれたいという気持ちの源泉がそこにある。
原因は絶対にある!諦めないことを学んだある事件

中山事務所のポリシーは「諦めない」ということであった。
ある若者が一酸化炭素中毒で死亡した案件があった。中山事務所はその遺族から依頼を受けたが、死亡原因が不明だった。警察に聞きに行っても、捜査中ということで詳細は教えてもらえなかった。事故から3年が経過しようとしていた。原因不明のままであったが、諦めずに訴訟を提起した。その後も警察から捜査結果の説明はなかったが、裁判所には辛抱強く待ってもらった。しかし、さすがにこれ以上は待てないと言われてしまう。大ピンチである。
ところが、警察に定期的に顔を出し、粘り強くお願いを続けるなどの一生懸命さが認めてもらえたのか、事態は急転直下を迎えた。ガス湯沸し器の安全装置がショートカットされていたという事実が明らかになり、事態が大きく前進したのだ。結局、崖っぷちから大逆転の勝訴判決を受け、新聞でも大きく報道された。
その後、その記事を見た同種事件の遺族から事務所に電話があった。その遺族は弁護士と相談したが、原因が分からない以上、どうしようもできないと言われ、諦めていたというのである。この時点で、事故から3年が経過していたが事故の原因を知らなかったのだから時効は完成していないと主張して、別途訴訟を提起して、これも勝訴した。このメーカーの湯沸かし器の問題が大きく話題となったのはそのずっと後のことである。
【1993年】弁護士駆け出し時代〈 II 〉
法廷の中で学んだ弁護士としてのスキル

スポーツでは「勝ち試合から学ぶことは少ないが、負け試合からは学ぶことが多い」と言われる。弁護士の世界でもそうだ。特に尋問の技術は、座学では絶対に身につかない。「してやられた」と思う尋問を目の前でされることも多かった。自分がされると苦しい尋問のやり方を知ると、それを次に生かすことが大切だと思った。
準備書面に「主張自体失当」と書いて、相手方のベテラン弁護士を烈火のごとく怒らせてしまったことがある。感情的な表現は、相手方弁護士のやる気に火をつけ逆効果となるということを学んだのもこの頃である。
先輩の姿を見て勉強した弁護団活動
弁護士としてどうあるべきかは、他の弁護士の活動を見て学ぶしかない。当時はどの新人も何らかの弁護団に加入して事件に関わり、弁護団会議の中で学習していったものだ。私は「金属じん肺事件」「太田国賠事件」「晴山再審事件」などに関わった。関わったと言っても本当に僅かであったが、それらの活動から、どのような弁護士が周囲の尊敬を集めるのかを知ることができた。
楽しかった公害環境委員会での弁護士会活動
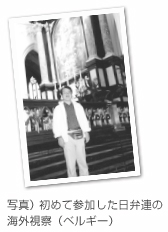
表現は適切ではないが、当時の弁護士会活動には、遊び心や余裕があったように思われる。私も公害対策・環境保全委員会では、日頃の業務や裁判と直結しないことから、純粋な気持ちで活動し、士幌高原道路や千歳川放水路などの問題で弁護士会の活動が大きな成果を収める場面に立ち会うこともできた。
この委員会の先輩が強く勧めてくれた、日弁連の公害対策・環境保全委員会の海外視察(ベニスでの国際環境裁判所設置に関する会議)の参加は、大きな財産になった。視察中、井の中の蛙だった私は、日弁連で活動する弁護士のスーパーマンぶりに驚かされ、途中立ち寄ったデンハーグ(オランダ)の国際司法裁判所では、小田判事からヒアリングをするなどの貴重な体験もさせてもらった。そしてこの海外視察の経験が、札幌弁護士会公害・環境委員会単独でのドイツ環境首都の視察につながった。この視察に参加した若手弁護士が、後に公害環境委員会の中心になってくれた。
胃痛から始めたテニス約20年間週2回を継続
弁護士としてフルに活動して8年程経過した頃、胃痛に苦しむようになった。様々な検査の結果、胃痛の原因はストレスという結論となったため、ランニングを開始。しばらくすると胃痛は生じなくなったが、冬に中断すると再発した。そんなとき、ボスを見習ってテニスを始めてみることに。ボールに集中するテニスは、プレー中に事件のことを考える余裕はなく、ショットの時に大声を上げると気分もすっきり。ストレス解消にはもってこいだった。人脈が広がったのもテニスの成果である。
弁護士と名乗るだけで得られた信用

新人でも「弁護士」という肩書きがあれば、お客さんや相手方から高い信用を得ることができた。それは本当にありがたいことで、様々な弁護士会活動や訴訟活動によって「弁護士」の信用を高めてきた先輩方がいたからであると思う。だから、委員長をお役御免になる年代までは、私も一生懸命、弁護士会活動に取り組んできたつもりだ。今、弁護士と名乗っても、それだけでは信用されない。必ず、どのような弁護士かを調べられる時代である。弁護士の信用を落とすことがたくさん起きているということなのだろう。
【2003年~2005年】独立時代〈 前期I 〉
平成8年、独立忘れられない「事務所開き」の思い出

中山博之法律事務所には4年契約で入所したが、中山弁護士が札幌弁護士会の副会長になったことから独立が半年遅れ、平成8年1月に独立をすることとなった。
当時は、札幌弁護士会は牧歌的でアットホームで、全体で200名程度、毎年加入する弁護士が10名前後だったから、1人1人の顔と名前が一致する時代で、弁護士が独立すると事務所開きと称して、事務所をお披露目し、多くの弁護士がご祝義を持って集まってくれた。私も「事務所開き」を行わせていただき、多くの弁護士の前で、家族そろってご挨拶をさせていただいた。中山先生や中山事務所の二代目イソ弁の森越壮史郎弁護士、同期弁護士からも激励のご挨拶、多くの花束を戴いた。この時の感動は今も忘れられない思い出であり、私の弁護士人生のハイライトの―つだ。
医療訴訟への取り組み
当時、医療訴訟の患者側は、医療に関する知識も少なく、医師の協力も得られる機会が少ないことから不毛の時代だったが、この分野のパイオニアである名古屋の加藤良夫弁護士の呼びかけに呼応して、上田文雄弁護士や中山弁護士が中心となって札幌で医療訴訟弁護士団を作ることになり、その原始メンバーに人れてもらえることになった。メンバーは当初20名前後で、それぞれ5名程度の班をつくり、医療事故で泣き寝入りするしかない患者を救おうというスタンスで無料相談や事件を担当、弁護団を立ち上げた。
班は、AからDまで4つあり、私はC班だった。C班として、私が最初に関わった事故が麻酔事故であった。「麻酔をかけたらだめな身体だったのに、麻酔をかけられたために夫が死亡した」という判じ物のような妻の訴えから調究がスタートした。最初は麻酔にアレルギー反応があるということなのか、半信半疑だったが、以前手術を受けたことがある病院から医療記録を取り寄せたところ、患者は「猪首」で気管挿管がしづらい体型で、実際、手術の際は挿管ができずマスクに切り替えて手術をようやく成功させていたことが判明した。
勝てるという確信のもと、毎回準備書面を作成し、同じC班のベテランの北潟谷仁弁護士に何度も添削をしていただいた。徹夜に近い作業を繰り返して、ついに逆流性食道炎に罹患するまでになったが、努力は実り勝訴となった。この事件で患者の声を素直に聞くことの重要性、粘り強く諦めずに取り組むことの重要性を学んだ。最初の事件が大きな成果を出したことが、その後私を医療訴訟の世界にのめり込ませる結果となった。
楽しかった公害環境委員会での弁護士会活動

表現は適切ではないが、当時の弁護士会活動には、遊び心や余裕があったように思われる。私も公害対策・環境保全委員会では、日頃の業務や裁判と直結しないことから、純粋な気持ちで活動し、士幌高原道路や千歳川放水路などの問題で弁護士会の活動が大きな成果を収める場面に立ち会うこともできた。
この委員会の先輩が強く勧めてくれた、日弁連の公害対策・環境保全委員会の海外視察(ベニスでの国際環境裁判所設置に関する会議)の参加は、大きな財産になった。視察中、井の中の蛙だった私は、日弁連で活動する弁護士のスーパーマンぶりに驚かされ、途中立ち寄ったデンハーグ(オランダ)の国際司法裁判所では、小田判事からヒアリングをするなどの貴重な体験もさせてもらった。そしてこの海外視察の経験が、札幌弁護士会公害・環境委員会単独でのドイツ環境首都の視察につながった。この視察に参加した若手弁護士が、後に公害環境委員会の中心になってくれた。
刑事事件で無罪判決
中山弁護士が全国的に見ても有数な刑事弁護人だったので、刑事事件にも懸命に取り組んでいた。イソ弁時代に、ガソリンスタンドで覚せい剤を使用中に警察の職務質間を受けた被疑者が、乗っていた車で逃げようとして給油機にぶつかってしまい破損させ、覚せい剤取締法違反と器物損壊罪に間われた事件で、給油機にぶつけるという故意はなかったと主張して無罪を獲得した。また、独立してからも放火事件で一部無罪を獲得し、有罪とされた事件については最高裁まで争い、最高裁で保釈決定を取るなどの結果を残すことができた。また、殺人後、被害者から財布を取ってしまったという案件で強盗殺人に問われた事件では、財物奪取の意思は殺人後に生じたものだ、殺人+窃盗に過ぎないとして争い、捜査段階では連日接見をして、被疑者を励ました。毎日面会して信頼を勝ち得ていたと思っていたが、後日、被疑者に「本当は敵対しているはずの検察官の方が弁護人よりも親身に自分のことを考えてくれていると錯覚してしまった」と告白され、挫折感を覚えたことを鮮明に覚えている。残念ながら弁護人の主張は認められなかった。
私にとっての最大の刑事事件は、拓銀の元経営陣に対する特別背任事件だろう。この事件のことは知っている人も多いだろうが、次回に書こうと思う。
弁護士会の視察で海外へ家族で映画の舞台も巡った思い出
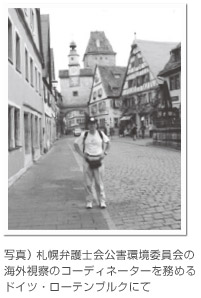
弁護士会の活動では、公害対策・環境委員会で副委員長になり、日弁連公害対策・環境委員会委員として日弁連活動にも参加した。日弁連では、自然保護部会に所属して、さまざまな自然保護問題のシンポジウムの企画に参加し、海外視察にも結構出かけた。最初は、視察にただついていくだけであったが、後にコーディネーター役に抜擢されるまでになった。
一番のハイライトは、ウィーンからミュンヘン、ケルンを巡った視察だろうか。この時は都市計画の視察であったが、その前後に楽しい個人旅行が組み込まれていた。せっかくの機会だからということで、参加メンバーの家族も参加した。私も、当時幼稚園に通っていた娘と家内を伴って参加した。ウィーンに入る前に名作「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台を巡る旅をした。素晴らしい風景だったが、そこがトラップ一家がボートをこいで転覆したムントゼーであることや、ドレミの歌を歌ったミラベル庭園であることなども知らずに巡っていた。帰国してから映画をレンタルして観て、「ああ、あの場所だ!」と親子して叫ぶシーンばかりであった。本当にもったいないことをした。
【番外編】父との思い出 ~ぽっぽやの道を貫いた人生~
狸小路で生まれ育ち樺太移住を経験した戦前戦後
昨年10月、父を亡くした。父親は昭和8年(1929)生まれ。同い年の故人では小沢昭一、村田英雄、大川橋蔵、向田邦子がいる。世界恐慌から第二次世界大戦へと向かう大変な時代だった。実家は狸小路1丁目界隈にあった洋裁店。父は札幌がまだ牧歌的な時代に豊平川で泳いだり、帝国座に映画を観たりして遊んでいた。当時栄えていた狸小路にお店があったので、そのまま過ごしていれば戦後それほど苦労はしなかったのだろうが、一家は一旗揚げようと樺太に渡る。
樺太の最南端大泊(現在のコルサコフ)というところに移住したが、間が悪いことに樺太に渡ってすぐに終戦を迎えてしまう。無事、札幌に戻ったのは良いが、狸小路の店は人手に渡り、そこに戻ることができず、実家は山鼻付近で洋装店を営むことになった。
洋裁の仕事を継がず国鉄マン一筋の道へ

終戦を迎えた時、父は17歳。洋裁の仕事を継がず、進駐軍の列車で働くようになり、その後、国鉄の車掌へ。以来、国鉄がJRに変わる最後の年に退職するまで、国鉄マン一筋だった。
戦後から長い間、国鉄は蒸気機関車が中心で、函館や釧路に出かけたら一泊するのが勤務の常識だった。函館で一泊して翌日戻るという勤務の中で、函館駅前のお店で働いていた母と知り合い、結婚して、昭和33年(1958)に私が生まれた。
父は、普段は寡黙、酒が入ると多弁となり、時として騒動を巻き起こすこともあった。職場の友人の方に聞くと、職場では温厚そのもの、酒が入ると鼻と下唇の間にマッチ棒を立てて、ドジョウ掬いを踊り出すという人気者で通っていたという。その分、自宅では酒が入ると鬱積したものがあふれ出てしまったのかもしれない。
どんなことがあっても休んではならない
さて、検察修習では目が回るような忙しい修習だったのが、裁判修習ではじっくりとした修習となり、時間がゆったりと流れていった。しかし、いよいよ弁護修習が始まると、その時間の流れは想像以上に激しく厳しいものに変わった。
当時修習を担当してくださる修習担当の弁護士は担当弁護士が引くくじで決まるのが習わしで、私は磯部憲次先生のところで修習することに決まった。
磯部憲次先生の指導は極めて厳しいものであった。磯部先生からまず言われたのは「弁護士は健康こそ最も大事で、どんなことがあっても風邪であっても交通事故にあっても這ってでも仕事に出なければならない」ということだった。
ところが、間が悪いことに言われてすぐに風邪を引いて休む羽目になった。風邪で寝込んでいたら、磯部先生から電話が来て、やりかけの起案を完成させないまま事務所を休んでしまったことについて注意を受けたのである。
また、磯部先生が事情を聴取しているときに私が介入し、他愛もない話題を顧客に話しかけ場を和ませることがあったが、顧客が帰ってから、途中で話の腰を折るような言動を慎むよう諭された。このエピソードは修習から20年以上経ても記憶に残っているのだから、よほど当時の自分には堪えたのであろう。
お酒が入らない限り、父は優しかった。私が高校へ進学するまでは真駒内に住んでいて、たびたび昆虫採集に連れて行ってくれた。近くの桜山へクワガタやセミ採りをしたり、旧進駐軍住居跡地で当時は警察学校のあった場所にキリギリスを採りに出かけたりもした。また時には、石狩当別の釜屋臼(かまやうす:現在のあいの里公園)にまで足を運び、フナやドジョウ釣りも教えてくれ、父親と一緒に楽しんだ情景が思い出される。
花形路線・函館本線の専務車掌として活躍する日々
松本清張の小説「点と線」でも取り上げられているが、父の働いていた時代は飛行機がほとんど普及しておらず、札幌から東京までは青函連絡船を利用しての鉄道での旅行が一般的だった。当然のことながら車掌にとって、乗客が多い札幌~函館間は花形路線だった。父からは有名歌手(春日八郎や三浦浩一)や関取(柏戸)を乗せたという自慢話をよく聞かされていた。
その後、父は一念発起して車掌を束ねる専務車掌を目指し、見事合格を果たす。しかし、専務車掌の定員は満杯。誰かが退職してポストが空くまではローカル線の車掌を務めなければならなかった。それまで食堂車付きの花形路線で活躍していただけに、手弁当で万字線などのローカル線に一人で乗車するのは非常に辛い日々だったと思う。
やがてポストに空きが出て、専務車掌になることができた。現在はテープによる無味乾燥な男性の声の案内が流れるが、当時は鉄琴のメロディーとともに、車掌自らが生で到着駅の案内をしていた。特に、函館本線では大沼国定公園や駒ヶ岳などの名勝を案内するのが習わしで、父は、この案内が非常に上手だった。
国鉄を退職する間際、札幌駅まで父の写真を撮影しにいったことを覚えている。真っ白い制服を着た写真が一枚残っている。父の絶頂の時といえるだろう。
豪雪の出来事自覚させてくれた父の怒り
退職後は、私の受験が重い影を落とした。父が退職したのに、息子は未だに宙ぶらりんのまま、合格もせず、自宅にいる。それでも父親は黙って面倒を見てくれた。そのストレスやいかばかりかと思う。
それが爆発したのは昭和63年(1988)の冬のことである。大雪の日だった。父は雪かきをしているうちに、雪かきもせずに黙って室内にいる私に腹が立ったのだろう。私も父親に窓越しに雪をぶつけたこともあり、烈火のごとく父は怒った。それまで父の車を北海道大学給湯室まで通うのに使っていたが、その車も取り上げられてしまう。その後はもう針のむしろ状態。私は、この家には居られないという気持ちが募る一方だった。背水の陣である。
幸い、その年、火事場の馬鹿力で最終合格を果たすことができたが、あの豪雪の日の出来事がなければ甘えがでて合格できなかったかもしれない。
今自分も一人の父親となって、父の気持ちを追体験しているが、受かる保証などない司法試験にチャレンジすることをよく許してくれたと感謝する気持ちでいっぱいだ。
鉄道員だったことを忘れていなかった最期
その後、父は北海道犬の「ドン」や野良猫の「ニャン」を可愛がりながら、自宅の庭いじりを楽しむ生活を送っていた。やがて認知症状が重篤となり、入院生活を余儀なくされた。晩年、父は朝起きると、母に「国鉄車掌区から電話が来て今日乗車してくれと言われたので、車掌の制服を出しておいてくれ」とよく話していたそうだ。
最後の最後まで気持ちは鉄道員だったのかもしれない。




